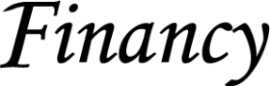テレビのニュースを見ていると最後の方に日経平均株価やTOPIXなどの指標と合わせて、ドル円やユーロ円などのレートが表示されることが有ります。円と外貨の交換レートは常に変動しており、円の価値が高くなることを円高、安くなることを円安と言います。一体円高や円安という現象はなぜ起きるのでしょうか。
実は円高・円安の原因は、一般的な商品が高くなったり安くなったりするのとあまり変わりありません。人気があって需要が供給を上回る商品は高くなり、人気がなく需要が供給を下回る商品は安くなります。それと同じで円の需要が供給を上回れば円高になり、円の需要が供給を下回れば円安になります。では、円の需要は一体何故増えたり減ったりするのでしょうか。
円高・円安の原因は国境を超えたものやサービス、通貨交換
円高・円安は基本的に外国との通貨のやり取りがなければ発生しません。もしすべての国が完全な鎖国政策を取っていたら、固定相場制でも問題は起こらないはずです(すべての国が完全な鎖国をしているのに為替はそもそも不必要になりますが)。
例えば、日本の商品をアメリカの企業が買う場合について考えます。この場合、日本の企業はアメリカの企業から貰ったドルを円に交換します。そうした企業が増えれば円の需要が増加し、円高になります。
一方でアメリカの商品を日本の企業が買うこともあります。この場合、アメリカの企業は日本の企業から貰った円をドルに交換して買います。そうした企業が増えれば、円を売りたいという需要が減少し、円安になります。
また、商品を介さずに直接外国の通貨を買うこともあります。例えば、日本の銀行預金の金利がアメリカのそれよりも明らかに高くなった場合、アメリカ人は日本の金融機関に預金したいと考えるようになります。日本の金融機関は円での預金を受け付けるので、アメリカ人は日本円を買います。そうした個人が増えれば円の需要が増加し、円高になります。
逆にアメリカの銀行預金の金利が日本のそれよりも明らかに高くなった場合、日本人はアメリカの金融機関に預金したいと考えるようになります。アメリカの金融機関はドルでの預金を受け付けるので、日本人は円を売ります。そうした個人が増えれば円の需要は減少し、円安になります。
現代においては、輸出や輸入などのものを挟んだお金のやり取りよりも、直接的な通貨の売買のほうが需要が多く、それがより為替に大きな影響を与えます。様々な個人、もしくは法人の投資のプロは様々な国の政治、経済、社会の抱えている問題や情報、国民性などを分析し、どの国のお金を買い、あるいは売るかを決めています。
貿易黒字は円高を促進する?
日本は(外国もそうですが)、海外に様々な商品を輸出する一方で、海外から様々な商品を輸入しています。仮に輸出が輸入を上回っていた場合は貿易黒字、逆の場合は貿易赤字と言います。
仮に輸出が輸入を大きく上回る、貿易黒字になっていたとしましょう。その場合、日本企業は多く外貨を手に入れ、それで多くの円を買います。一方で海外企業は余り日本円を手に入れないので、売られる円は少なくなります。円の需要の量が増えるので、円高が進みます。
しかし、円高が進むと今度は輸出が鈍ります。円高だと輸出をしても儲からなくなるからです。例えば、1ドル=100円の時にアメリカ企業に1万ドルで商品を売れば100万円の売上ですが、1ドル=80円の時に売っても80万円にしかなりません。一方で海外製品は安く変えるようになるので、輸入は伸びます。すると貿易赤字になります。
貿易赤字になると、貿易黒字のときとは逆に円の需要が減り、供給が増えるので円安になります。円安になれば輸出は復活するので再び貿易黒字となり、今度は円高に傾きます。
しかし、最近は貿易収支と円高・円安が必ずしも理論通りに動かないことがままあります。
経常収支と円相場の関係
経常収支とは、「貿易収支」「サービス収支」「所得収支」「経常移転収支」の4つからなる指標で、一刻の国の収支を表すものです。
貿易収支とは
貿易収支とは、前述の貿易黒字・赤字云々の話です。たとえ貿易収支が黒字でも、それ以外のサービス収支、所得収支、形状移転収支を含めた全体の経常収支が赤字だと、円安方向に動きやすいものです。
サービス収支とは
サービス収支とは、日本に旅行に来た外国人が落としたお金と、海外に行った日本人が現地で落としたお金の収支です。例えば日本に旅行に来た外国人が日本でお金を使えば円の需要が高まって円高になりますし、日本人が海外でお金を落とせば円の供給が増えて円安になります。
所得収支とは
所得収支とは、海外の日本企業など海外で稼いだお金を国内に送った額と、海外の企業が日本で稼いだお金を母国へ送った額の差です。海外の日本企業が海外で稼いだお金を国内に持ち込めば円の需要が増えるので円高となり、逆に場合は円安になります。
経常移転収支とは
経常移転収支とは、海外への途上国援助です。日本は途上国援助をしていますが、他所の国から途上国として援助は受けませんので、ここは常に赤字となり、円安要因となります。
通貨の信用力が高いと通貨高になる?
日本や海外で発行されている通貨は、絶対的に信頼できるものではありません。国家とはいえ破綻する可能性はゼロではないからです。自分の持っている通貨を管理する国の政府が突然破綻してしまったら当然困ります。
そこで一部の投資家は、いざという時に備えて安全な通貨を持とうとします。安全な資産とは要するに破綻の可能性が低い(信用力が高い)国の通貨です。信用力の高い通貨を欲しがる人は多いので、その分、通貨高になります。
ただ、どの通貨が信用できるか、という判断は人によって異なるでしょう。たとえ経済アナリストが信頼できる通貨だと言っている通貨であっても、信用できない人は信用できません(そもそも経済アナリストという肩書の人がどこまで信頼できるのかも疑問です)。なんとなく信頼できそう、程度の考えで通貨を選ぶ人がどれくらい居るのはわかりませんが……。
円高と円安、投資に向いているのはどちら?
理論も大切ですが、やはり多くの人が気になるのは円高と円安ではどちらが儲かるのか、ということです。結論から言ってしまいますと、投資の種類にもよりますが概ね円安のほうが投資には有利です。
株式投資の場合
株価は様々な要因に左右されますが、やはり一番大きなのは業績です。業績が上がればだいたい株価も上がります。そして前述の通り、円高だと売上が下がってしまうので、どうしても業績が上がりにくいのです。一方、円安だと売上が上がるので、業績は上がりやすくなります。株式を中心にした投資信託もほぼ同じです。
ただし、輸入した原材料を加工して日本国内で売る事業者(電力会社や製紙会社など)は円高で業績が上向くこともあるので、一概に円高だと稼げないとも言えません。
日経平均株価とドル円レートの相関グラグ

日本の株式市場は、ドル円の為替レートに大きく影響を受けます。2016年1月~2017年3月まで、日経平均株価とドル円レートの相関グラグを見ると、チャートのオレンジ線とブルー線が、かなり相関した動きをしていることが分かります。
債券投資の場合
円高が進むと輸出が鈍り不景気になるため、デフレが進みます。それとともに新初債券の金利は低下するので、既存の債券の価値は高まり、債券相場は上昇します。逆に円安が進むと新発債券の金利が高くなるので既存の債券の価値が低くなり、債券相場は下落します。ただ、債券はそもそも株式と比べると相場が低いのでこう動かない可能性も高いです。
FXの場合は売りから入るか、買いから入るかによって、円高・円安のどちらでも稼ぐチャンスが有ります。
関連記事:
→海外投資/オフショアファンドの窓口【IFA無料紹介サービス】
→日本と世界の学資保険比較!元本保証140%の海外積立商品
→海外積立投資メイン3社の比較と評判
→ヘッジファンドは投資信託比較で手数料10倍!でもリターンは3倍!?